30年前、“すすきの”のミニシアターが熱狂を呼んだ。とあるカメラ店の物語

鮮やかな緑に色づいた街路樹の通りを抜けると、まるで映画のセットの一部を切り取ったかのような、ブリキの外壁が目に入ります。
ここ「バンザイカメラ」は、札幌市内でも珍しい、フィルムカメラと8mmカメラの専門店です。人一人がやっと通れるほどの店内には、昔懐かしいデザインのカメラやレンズ、カメラバッグがところ狭しと並びます。
バンザイカメラを26年前から経営するのは、71歳の店主、木村純一さんです。木村さんは、かつてすすきのでミニシアター「ジャブ70ホール」を経営していましたが、1992年に閉館。その後は個人事業主としてお店を切り盛りし、現在のバンザイカメラの形となりました。

バンザイカメラにあるのは、9割が中古のフィルムカメラで、残り10台ほどが8mmカメラ。8mmカメラとは2007年に絶版になった、8mm幅のフィルムに映像を記録する仕様の、小型のビデオカメラです。約10年前まで8mmカメラを専門に扱っていたバンザイカメラですが、その存在を知る人が減るとともに需要も減り、新たにフィルムカメラを売り始めました。
昼下がりのバンザイカメラには、木村さんいわく「カメラオタク」の学生や20代の若者が訪れます。SNSでフィルムカメラで撮った写真が人気を集めているせいか、彼らはレンズやフィルターのことを熱心に質問したり、購入したりしていくそうです。

しかし実は、木村さんが好きなのはフィルムカメラでも8mmカメラでもありません。フィルムカメラは店の稼ぎ頭、8mmカメラは木村さんの中で“一番小さな映画”のようなもの。
木村さんがミニシアターを経営していたころは、今の映画館がやっているようなデジタル上映ではなく、35mm幅のフィルムを回して映画をかけていました。フィルムには、35mm幅、16mm幅、8mm幅のおおまかに3種類があり、「さほどお金をかけずに、手身近に映画にかかわれるのが8mmだった」と木村さんは語ります。
そう、木村さんが愛するのは映画。8mmカメラは当時、一般家庭がホームビデオとして使用する以外に、アマチュアの映画製作者が「8mm映画」を撮影する機材としても重宝されていました。木村さんが初めて8mm映画を撮った日、その物語は動き出したのです。

映画を年に500本観た学生時代
木村さんは1951年に、北海道帯広市で生まれました。
「親父が映画好きだったんです。一番記憶に残っているのは、小学生のときに親父が観に連れていってくれた、『大脱走』というスティーブ・マックィーンの映画。当時はあまりの面白さに病みつきになりました。映画の帰りには、近くの中華料理屋さんで餃子を食べて帰る……っていうのが、お決まりの流れでした」
父親と映画館に行き、帰りに2人で外食をする。外食をする機会などめったになかった幼い木村さんにとって、それは特別な一日でした。
帯広市内の中学・高校を卒業した木村さんは、東京の専修大学へ進学します。「東京へ行けばもっとたくさん映画を観られる」と思ったのです。
東京では、文芸坐(現・新文芸坐)や並木座などの「名画座」や、映画を観られる喫茶店、小ホールを映画雑誌「ぴあ」で調べ、通いつめました。名画座とは、旧作映画を安く上映する映画館のことです。木村さんは大学4年間、1本500円の映画を年間約500本ほど観たといいます。

大学を卒業した木村さんは、北海道へと戻り、就職先のあてもないまま札幌へ移り住みました。
「札幌で、どこかにたくさん映画観られるところないかなぁ……って探していたら、スガイビルが目に入ったんです。スガイビルは、建物内に映画館が11個も入った、地上8階、地下2階建てのビルでした。中へ入って『ここに勤めたいんですけど』と話をしたら、『いいですよ』って」
なんと木村さんは、札幌の大手興行会社「須貝興行」の自社ビルにアポなしで乗り込み、内定を取りつけたのです。須貝興行は当時、道内最大規模と言われた約500席の「札幌劇場」をはじめ、複数の映画館をスガイビル内で展開していました。「これでタダで映画が観られると思った」と、木村さんは笑います。1976年、25歳のときでした。
「そうだ、映画館をつくろう」
木村さんが任されたのは、スガイビルの地下にあったミニシアターの事務スタッフ。そこで出会ったのが、木村さんと同年代の2人の青年です。彼らは熱烈な映画ファンで、すぐに意気投合しました。以来、3人で館内イベントやお祭りを企画したり、15時になると休憩がてら「3時会」と称して、ビールを片手に映画について語らったりするのが日課になりました。
月収は14万円、ボーナスなし。「給料は高くなかったけれど、それでも楽しかった」と木村さんはいいます。一方で木村さんは、自分たちのはたらく映画館について、あるモヤモヤとした気持ちを抱いていたのも事実でした。
たとえば、現代の映画館は上映予定時間があらかじめ決まっていて、その時間に間に合うように入場する人が大半です。自ら好んで遅れて来る人は少なく、シアター内で食べるものは、匂いや音の少ないポップコーンやホットドックが一般的です。
ところが木村さんが当時目にしていたのは、途中入場があたり前で、館内で匂いの強い“さきいか”や、ボリボリと咀嚼音がする豆菓子が売られ、シアター内で食されている光景でした。
加えて、エンドロールが流れている最中に照明が明るくなるなど、映画が好きな人ほど、心置きなく楽しめるとは言い難い環境でした。「東京では改善の動きがあったかもしれないけれど、札幌はほとんどの映画館がそうだった」と木村さんは振り返ります。

あるとき、木村さんと2人の青年は、遊びの一環で8mmカメラで映画を製作しました。タイトルは『長いお別れ』。これを「ぴあフィルムフェスティバル」という自主製作映画のコンペに応募したところ、審査を通過し、スガイビルの地下のシアターで一般公開する許可が出たのです。これが大ヒット。アマチュア3人が製作した8mm映画にもかかわらず、500人のお客さんが詰めかけました。そこで木村さんたちは思いました。
「そうだ、自分たちで映画館をつくろう!」
そうすれば「正しい映画の見方」ができる──。以来木村さんたちは、毎月お給料が出ると“3時会”の場で1人1万円を出し合って設立資金を貯め始めました。
「1年後、30万貯まったところで、誰かが『よし、辞めるか!』と言い出して。30万で3人で会社を辞められると思ったの、すごいと思わない?(笑)でも、仲間がいたからね。一人じゃできなかった」
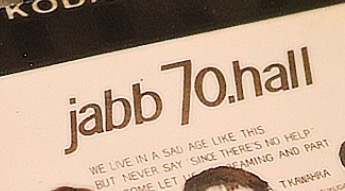
もちろん、140万都市(当時)の札幌の中心部に映画館を建てるには、到底お金が足りません。木村さんは、その足で銀行の窓口へ行き、「映画館を作りたいからお金を貸してほしい」旨を伝えました。会社を辞め、なんの後ろ盾もない木村さんに融資の許可が下りる可能性は低いように思われましたが、窓口の担当者が手渡したのは、「記憶が曖昧だけれど、たしか350万円」(木村さん)の手形貸付でした。
さらに、「ジャブをつくる会」を立ち上げ、そのチラシを須貝興行の関係者などに配ったところ、賛同した人たちや友人から100万円前後が集まりました。木村さんの取り組みを応援していた父親が国民金融公庫から借りたお金も入れると、資金は約1,000万円になったのです。
設立場所として選んだのは、すすきのの一等地にある、とあるビルの地下1階でした。座席はスペース的に50席も置けない、映画を写すための映写機は高価なためリースしか選べないなどの制約はありましたが、1982年1月、一風変わったミニシアター「ジャブ70ホール」が誕生したのです。
「途中入場は禁止で、開始時間になってもお客さんがゼロなら上映をやめる。さきいかは売らず、エンドロールが終わるまで照明はつけない。札幌でそれをやったのはジャブが初めてで、先駆けでしたよ。『途中入場できないなんてどうなってるんだ』と、文句もたくさん言われました」

「その代わり、シアター前のスペースには本を置いて、横の喫茶コーナーではコーヒーを飲めるようにしました。我ながらおしゃれな劇場でしたよ。今はよくあるかもしれないけど、当時は本を置いている劇場なんてなかったんです」

コアなファンに支持され、来場者が13万人に
初回上映は、7日間で約500人が来場しました。2作品目は約300人、3作品目は約700人。順調な滑り出しに思えましたが、現実は甘くはありませんでした。4作品目はなんと、1日目の来場者が0人だったのです。
「その日以外にも、お客さんが来ないことはよくありました。興行※は大変です。配給会社からタイトルを借りてきて、宣伝して、お客さんが来るのを待って……ああ、今回もまただめかぁって。いやぁ、思い出したくないね(笑)」
どれだけ経営が大変でも、自分たちの好きな映画を思う存分やれたならマシでした。しかし、ジャブ70ホールのようなミニシアターは、たとえば東宝や松竹、東映といった大手映画配給会社が配給する映画を、ほとんど上映できなかったのです。
木村さんによると映画は、映画製作会社が作った映画を映画配給会社が宣伝・配給し、それが映画館に下ろされて初めて上映できるのだといいます。
ジャブ70ホールは、こうした大手映画配給会社に属さない「独立館」。しかも、席数が少ないぶん見込める興行収入も少ないため、確実に大入りになる大型連休を除いて、人気の封切り映画(新作)が回ってくることはありませんでした。
※観客を集め、入場料をとって映画を上映すること。

「だから必然的に、マイナーな映画をやるしかなくなってくる。もう残りもの商売です。美味しいとは言えません。大手が作り上げたシステムに刺さり込もうと思っても、うまく入れないんですよね」
木村さんは考えました。そして、須貝興行にいたときのように、自分たちで映画を撮って上映すればいいと閃いたのです。普段はたとえ映画がヒットしても、売上の半分以上を映画配給会社に支払わないといけませんが、この方法なら全売上がジャブ70ホールに入ると。
すると、8mm映画の映像作家で、ジャブ70ホールでも何度か自身の映画を上映していた吉雄孝紀氏に、「木村さん、映画撮ろう!」と声を掛けられます。しかも、吉雄氏の頭のなかに描かれていた主人公のイメージは、木村さんそのものでした。

木村さんはこの映画で、主人公として俳優を務めました。これは全国のミニシアターのほか、世界的な映画祭や、香港の衛星放送で上映されるヒットとなりました。
また、マイナーで「美味しくない」と思われた映画の中にも、稀に“当たり”がありました。とくに、デヴィッド・ボウイ主演の『ジャスト・ア・ジゴロ(1978年)』は1日に800人のお客さんが訪れ、100人ずつを8回入れ替えて上映しました。このときは、48席のまわりに座布団を敷きつめたうえ、立ち見客もいたといいます。
同じく、ルキノ・ヴィスコンティ監督の『ベニスに死す(1971年)』や、ジョナサン・デミ監督の『ストップ・メイキング・センス(1984年)』も大入り。こうした「耽美的(たんびてき)な」アート映画は、ジャブ70ホールの看板となっていきます。アート映画とは、芸術性の高い、ニッチ市場向けに作られた自主製作映画のことです。
「映画ってね、劇場にお客さんがつくんじゃなくて映画につくから、タイトルによってお客さんの層が違うんですよ。それでも、劇場と映画のイメージがぴったり合うと、比較的大入りになる。これらは、ジャブ70ホールで上映したから人気が出たという自負はありました」
1987年、コアで熱狂的なファンのついたジャブ70ホールは、累計来館者数が13万人に。札幌の映画ファンの間で、一世を風靡したのです。
同じころ木村さんは、ジャブ70ホールと同じフロアに「ジャブパート2」をオープンしました。ジャブ70ホールはマイナーなアート映画の名画座になっていたため、同じアートでも、「封切り(新作)映画」専用のシアターがほしかったのです。1作品目は21日間で2,000人以上、2作品目は7日間で1,000人以上が訪れました。
ところがジャブパート2は、封切り映画専用ということで入場料を3倍の1,500円にしたせいか、次第に開業閉店状態に。ジャブパート2の維持費は、ジャブ70ホールの懐を圧迫していきます。もともと「同じ映画は2度上映しない」と決めていた木村さんたちでしたが、すでにそのようなことも言っていられず、過去に大入りを記録した映画を再上映したり、宣伝に力を入れたりと、あらゆる手を尽くしました。
「公営住宅に住んで、女房もはたらいてた。それでも、最低14万円は給料として確保できるように、必死に稼いで貯め込んで。それはもう大変でした」

当時、息子と娘は小学生。奥さんは木村さんの挑戦を一度も反対しませんでした。それでも、赤字を補填するお金がなくなったとき、ジャブ70ホールと、同じフロアにあったジャブパート2は10年間の歴史に幕を閉じることとなります。1992年、木村さんは41歳でした。
「自分で生きていくしかない」と悟った
ジャブ70ホールの閉館後、木村さんはバンザイカメラの前身となる店を、すすきのから車で12、3分の住宅街に開業します。とはいえ、経営の大変さは痛感したはず。もう一度、会社員に戻ろうとは思わなかったのでしょうか。
「『俺にできることって何があるかな?』って考えたら、映画のことしかないと思って。すすきののレンタルビデオ屋さんに行って、『面接を受けさせてください』と伝えたんです。そうしたら先方が俺のことを知ってて、『あなたみたいな人使えませんよ』と言われて。頑張って行ったつもりだったけど、そっか、俺って使いづらいんだなってショックを受けました。それで、もうどこかに所属するんじゃなく、自分で仕事を見つけて生きてくしかないと悟ったんです」
最初に売ったのは、カメラではなく「駄菓子」でした。映画を観ていたら駄菓子屋が出てきて、感覚的に「面白そうだ」と感じたのです。30年前とはいえ駄菓子屋は札幌では珍しく、開店と同時にテレビの取材が来るなどして大繁盛。「家族連れが車でバンバン来て、1日にものすごい数が売れた」といいます。
「でも駄菓子って、利益が1割しか出ないから、1万円売っても1,000円にもならない。そんな状況だったので、ある日、もっと高単価で、風景的にもおしゃれだからと、古い8mmカメラを一緒に置いてみたんです。でもよく考えると、10円や20円の駄菓子を求めてやって来るお客さんが、3,000円や5,000円のカメラに興味をもつわけがないんですね。目的が違うから。それで駄菓子をやめて、カメラ専門店にしました」
現在木村さんは、店舗販売に加えて、インターネットオークションやフリマアプリにもカメラを出品して生計を立てています。木村さんいわく、日本人は大のカメラ好き。界隈では「カメラはお金になる」と言われており、出品者が増えているそうです。当時小学生だった娘も、現在は木村さんに代わって、オークションの出品を手伝います。

バンザイカメラには、学生や20代の若者のほかにも、こんなお客さんが訪れます。
「中年の女性が、『あのときジャブ70ホールで観た映画が忘れられません』って、目をキラキラさせて話すんだよね。それは実はめちゃくちゃ(お客さんが)入らなかった映画なんだけど、お客さんにとっては1人で観ようが100人で観ようが関係ないから、きっと『北海道のジャブ70ホールという映画館で、あの作品をやっと探して観られた』っていう達成感があるんだと思います」
幼いころ、父親と観た映画に魅了され、すすきのにミニシアターまで立ち上げた木村さん。今も「映画にかかわっていたい」という想いから、バンザイカメラを営みます。
フィルムカメラの存在を「売上のためだよ」と話す木村さんですが、店内に綺麗に並べられたカメラと、それを大事そうに扱う木村さんの横顔を見ると、映画への溢れんばかりの愛情と同じだけの愛が、一心に注がれている気がしてなりません。
(文・写真: 原 由希奈)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。
あなたにおすすめの記事
同じ特集の記事
北海道武蔵女子短期大学英文科卒、在学中に英国Solihull Collegeへ留学。
はたらき方や教育、テクノロジー、絵本など、興味のあることは幅広い。2児の母。
人気記事
北海道武蔵女子短期大学英文科卒、在学中に英国Solihull Collegeへ留学。
はたらき方や教育、テクノロジー、絵本など、興味のあることは幅広い。2児の母。























