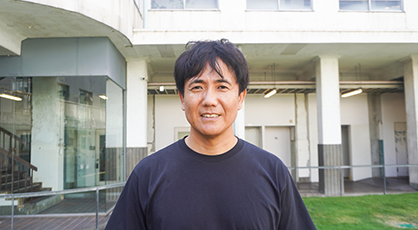交通事故の真実を突き止める。国内に20人だけの「交通事故鑑定人」

「交通事故鑑定人」は交通事故が起きてしまったとき、あらゆる角度から調査・分析をするスペシャリスト。残された証拠や資料から事故の様子を再現し、真実に迫る姿はまるで探偵さながらです。
現在、日本において警察や保険会社から独立した鑑定人として活動しているのは約20名ほど。そんなレアな仕事に従事して15年。株式会社NCSI代表の中島博史さんに交通事故鑑定の仕事についてお話を聞きました。
証拠を集め、CGで検証。探偵のように真実に迫る「交通事故鑑定人」
――交通事故鑑定とは、どういったお仕事なのでしょうか?
一言で表現すると「交通事故を理工学的に見て調査・分析し、その結果を踏まえて鑑定書を書く」仕事です。ただ、鑑定人によって得意分野やクライアントも異なりますし、調査方法も異なります。
――同じ職業といえど一様ではなく、鑑定人によってさまざまなんですね。
私は理工学的な視点からの分析を得意としており、弁護士さんから依頼をいただくケースが多いですね。「理工学的な分析が必要だ」と判断した際に依頼をもらい、裁判の資料として提出するための鑑定書を作成するのが主な仕事です。「この主張は成立しているのか」とか、「当事者の発言に矛盾はないか」といったことを調査しています。
――事故後の調査はどのように行っているのでしょうか?
弊社では、大きく分けて「現場検証」「CGによるシミュレーション」「計算」という流れを経て報告書を作成していきます。
まずは、基本的に現場に足を運んで、ブレーキ痕などの確認をしたり、事故当時の状況を再現し、動画や写真で撮影することが多いです。事故後に時間が経ってしまっている場合には、警察の実況見分調書や記録写真を取り寄せ「調書通りに事故が起きているか?」を検証しています。
――現地に足を運ぶこともあるのですね。
可能な限り足を運んでいますが、事故からの経過時間が長いと道路を補修されてしまったりすることもあります。鑑定人としてはできる限り事故車両を保存しておいてほしいんですが、保存には費用もかかるし、「見るのが辛い」ということで処分される方も多いですね。
――事故現場では、実際にその道を車で走ったりするんですか?
はい。同じ状況を再現して、当事者の目線からはどう見えているのかなどを確認します。必要な場合は、同じ車種を用意して実験することもありますよ。
――中島さんご自身で用意しているんですか?
そうです。バイクが横転して滑った場合、道路との摩擦係数は計算でははっきりした数値が出ないこともある。なので、バイクを購入して路面で引っ張ってみて、負荷がどのくらいかかるのかを検証する必要があるんです。
車の場合でも、同じ車を用意して、同じ道を同じように走って検証することはありますね。
――かなり手がかかっているのですね。現場検証の次は何をするのでしょうか?
現場ではどうしても再現できない状況や見ることができない角度があるので、それらをCG上で検証していきます。

――確かに、実際の現場に行っても同じ状況を再現することは難しいですもんね。
そうですね。具体的には道路台帳図から作図した三次元CGに車のモデルを配置してシミュレーションする、視野やヘッドライトの照らす範囲を再現するといったケースが多いです。
そして、現場とCGの検証で得た情報を元に、力学的な計算をしていきます。エネルギー量や事故時の速度など、裁判に必要なデータを割り出し、報告書としてまとめる。それを弁護士さんに提出するというのが一連の仕事の流れですね。
日本国内に20人だけ。鑑定人がレアな理由とは?
――実際に現地に足を運ぶとはいえ、記録やシミュレーションから事故の状況は正確に分かるのでしょうか?
最近だと警察の持っている情報に加えてドライブレコーダーの記録がありますので、詳細に割り出すことができますよ。動画からは近づいてきた速度や角度、あるいは衝突した瞬間に相手が何をしていたのかまで分かるので、検証の精度はかなり高まっていると思いますね。
――ドライブレコーダーの普及は鑑定人にとってはありがたいことですね。
10年ほど前までは交通事故の裁判は当事者同士の証言と、その主張の強さで裁判の結果が左右されていた。つまり、どちらが信用できるかという勘案で判決を出さざるを得なかったんですね。
しかし、ドライブレコーダーや街中に設置されている監視カメラが普及したことにより、客観的な証拠に基づいて話を進めることが前提になってきました。ドライブレコーダーの普及とともに年々事故件数は減ってきていますし、ありがたい変化ですね。
――どんな事故の調査が多いなど、依頼内容に傾向はありますか?
よくあるのは「一時停止線で停止後、交差点で車がぶつかってしまった」というものですね。このケースでは、一時停止をしたという主張の正当性を問うために調査をすることになります。
もし一時停止していたのであれば、ぶつかった位置までの間に最大どのくらいスピードが出せるかを割り出します。仮にそれが20キロだとしましょう。けれども、車の破損部を調査すると、50キロで衝突したと思われる壊れ方をしている。そのことから、一時停止はしたという証言の信憑性は低いと結論付けられます。
これはシンプルな例ですが、実際の調査では多角的な観点から検証を行っています。
――当事者の主張が必ずしも正しいとは限らないと思うのですが、そういったときはどうされているのでしょう?
調査していくと、実態と違うことを言っているという結論になることは多いです。個人から直接依頼をいただく案件では、裁判を有利に運ぶために依頼者の方が嘘を言っていることも少なくないですね。
――そういった場合はどうするんですか?
資料をいただいたところで予備的に調査をして「うちではあなたの主張を裏付けるようなことはできません」とお断りしています。弊社が弁護士からの依頼を中心に受けているのは、そうした事態を避けるためでもあるんです。
――交通事故鑑定のお仕事には、資格や制度はあるのでしょうか?
日本には公的な資格はありません。必要な知識やノウハウを学べる場所もないため、鑑定人になりたければ仕事をしている人の元で教えてもらうか、自学自習でやるしかないですね。
ドライブレコーダーの機能が進歩していったら鑑定士の仕事はなくなるんじゃないかなんて言われています。
――現在、交通事故鑑定人は日本にどのくらいいるのでしょうか?
20人程度ですね。私は工学部の出身ですけれど、保険代理店で事故を見てきた経験から始めた人もいますし、警察官として事故を見てきた方が、被害者の力になりたいと鑑定人になる場合もあります。バックグラウンドによって、得意分野もそれぞれです。
――そんなに少ないんですね。
交通事故裁判においては物理的な証拠よりも証言が重視されてきたんです。そのため、事実関係の裏付けがないまま、示談で終わってしまうこともよくあったんですよ。そうした状況だったので、鑑定の方法論を確立できるほどの実例が積み重なってこなかったんですね。資格がないということに加え、これも日本に事故鑑定人が少ない要因の1つだと思います。
鑑定人の道へ進むきっかけとなった、母親の事故
――中島さんはなぜ交通事故鑑定人のお仕事をはじめたのでしょうか?
工学系の大学で修士号を取得しソフトベンチャーに就職したのですが、そのころに母が交通事故に遭いまして。雪道を歩いている時に車に追突されて、障害が残るような怪我をしました。
加害者と母の説明は大きく食い違っていたのですが、現場は雪道ということもあり、物的な証拠が残っていない。母は病院に運ばれたため、警察の調書は加害者の話だけを参考に作られてしまった。その調書にはいろいろと辻褄が合わない部分があったのですが、それがそのまま通ってしまったんです。
これはおかしいと思って、私が相手の説明を分析して資料にまとめ、裁判所に提出したんです。しかし、素人のレポートなんて当然裁判官には読んでもらえないわけですよ。結果的に、母の裁判では負けてしまいました。
そんなことをしていたら、何人かの知人から事故の分析依頼がありまして。同じように困っていたり憤りを感じている人がいるんだということが分かってきたんです。それで、鑑定人の仕事を始めようと決めたんです。
――計算など専門性が要求される仕事だと思いますが、鑑定士としてのスキルはどのように身につけたんですか?
独学でしたね。計算に必要な知識のほとんどは、高校課程での数学、物理学くらい。なので、工学部を卒業する素養さえあればできると思います。
それよりも重要なのは、裁判において有効な資料にまとめるスキルです。そこは勉強だけでは身につかないと思います。
報告書は弁護士さんに理解してもらわないといけない。さらに裁判官に伝わらないと判決には影響しないので、裁判官に伝わるような形で書かなくちゃいけないわけです。そういったスキルは実際に仕事をしていく中で身につけていきました。実際、裁判官が見てくれるようになるまでは、何年もかかっています。
――そうだったんですね。スキルを学ぶ場がない、鑑定人が少ないなどの問題点を伺いましたが、今後鑑定人の仕事はどう変化していくべきだと思いますか?
そうですね……鑑定人の仕事というわけではありませんが、裁判に関わりながら、よく考えていることがあります。
日本では交通事故が起きた時、被害者の心のケアをしてくれるようなシステムがないんです。大きな事故の場合は、精神的に社会復帰できないまま人生がだめになってしまうケースもある。
弁護士ができるのは裁判のことだけですし、警察や裁判所は感情の面でケアしてくれるわけじゃない。そのため私に心理ケアを求める人もいるんですけど、専門ではないので力になれないわけです。メンタルクリニックの受診をすすめても、事故の経験をまた一から話すのが心理的ハードルになっているのか、なかなか受け入れてくれません。難しい問題ですね。
今後、交通事故で被害に遭った人の心のケアをする機関や、心のよりどころになるような場が、交通事故裁判のシステムの中に生まれていったら良いなと思っています。
(写真:鈴木渉 文:川浦慧)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。