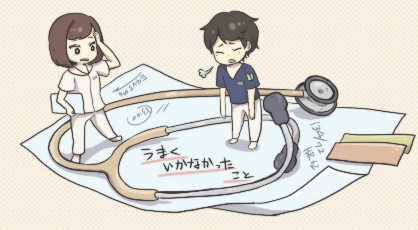- TOP
- "うまくいかなかった"あの日のこと。
- やる気だけでは乗り越えられないと知った日(大平一枝さん)
やる気だけでは乗り越えられないと知った日(大平一枝さん)

誰しも、“うまくいかなかった”経験があるはず。
そんな日の記憶を辿り、いま思うことを、さまざまな筆者が綴ります。
第1回目は、文筆家・大平一枝さんの寄稿です。

大平一枝
おおだいらかずえ 長野県生まれ。文筆家。編集プロダクション宮下徳延事務所を経て’94年独立。12年後に同事務所は解散した。著書に『男と女の台所』『もう、ビニール傘は買わない。』(平凡社)、『届かなかった手紙』(角川書店)、『あの人の宝物』(誠文堂新光社)他多数。連載中に『東京の台所』(朝日新聞デジタル)『そこに定食屋があるかぎり。』(ケイクス)など。
───
ごくたまに、「初めて書いた原稿のことを覚えていますか」と尋ねられる。そのたび、青い苦さがこみ上げ、胸の奥がぎゅっとなる。大失敗をしたために、忘れたくても忘れられないからだ。
ずいぶん回り道をして、26歳で念願の女性誌編集プロダクション(以下編プロ)に入社した。出版は、わからないことだらけの初めて触れる業界であるうえに、他の年若の社員よりスタートが遅い。とにかく先達に勝てるものは、やる気しかないと意気込んだ。
これが、穴があったら入りたいほどのミスの連続だった。
初めてのドラマロケの取材では、到着するなり撮影現場に突進し、カメラに写り込んでスタッフに怒鳴られた。推理作家に送る取材依頼書を、誤って芸人の事務所にファックスしたこともある。取材に向かう途中、新宿駅構内では迷子になり西口から東口へタクシーに乗った。一事が万事そんな調子で、空回りの日々が矢のように過ぎていった。

週刊誌編集部から独立して編プロを営んでいた社長(ボス)は教え上手で、一から出版のいろはを説いてくれた。誰に対しても丁寧に教えるので、ボスの名前をとって「◯◯事務所」ではなく「◯◯学校」と呼ぶ同僚もいた。
3年目あたりから、自分も編集だけでなくライターさんのように原稿を書いてみたいと思うようになった。ボスなら、原稿を指導してくれるだろう、給料をもらって教えてもらえるなんて、こんな得なことはないと。いつかフリーライターに、という思いはその時はなかった。
ただただやる気を見せたかったのと、原稿も書ける編集者なら万能だと思った。編集の仕事すらろくにできない新米なのに、思い上がっていたものである。
ある冊子で、素晴らしい画才で話題を呼んでいた身体的ハンディのある少女をとりあげることになったので、福祉を学んでいた自分にも書けるのではと思い切って申し出た。「このテーマにとても関心があるので、ぜひ書かせていただけませんか」
ボスは、じーっと私の顔を見てしばらく考えたあと、「じゃあやってみてください。原稿を見る時間が必要だから、早めに書いてね」とだけ言った。
張り切って単独で取材に行き、難なく書きあげた。なんだ、ライターさんってこんな少しの労力であんなに原稿料をもらっているのかと、とんでもない思い違いをしていることにも気づかず、悦に入っていた。
・・・
ボスの机の前で私は長い間待ち続けた。とうに読み終えているはずだが、彼は空(くう)を見つめながらタバコをふかし続けている。見出し一つで5回も6回も書き直しをさせる人だ。渋い表情から、こりゃ再提出で長丁場になるぞと腹をくくった。
やっと口を開いた彼に聞かれた。
「今日何日?」
「◯日です」
「締切まであと1週間だよね」
いつにもまして冷静な声に、嫌な予感がする。
「大平さん。ここからは編集者の頭に切り替えて。この原稿は使えない。あと1週間あってもだめだ。編集者なら、ここからどうする?」
1週間かけて指導しても商品にはならないと見限られたことにショックを受け、言葉が出ない。彼はもう一本タバコを吸ったあと、静かに指示した。
「時間がない。原稿を使えないとすれば、大平さんが取材したネタをデータ原稿にして、リライトできるプロのライターに大至急発注する。そうすみやかに判断するのが編集者の仕事だよ」
データ原稿とは、本原稿を書く記者やライターのために、必要な資料やネタを集め、粗原稿にしたもの。文字数に関係なく、取材で見聞きしたネタをできるだけ具体的にたくさん文字に起こす。これを集める人をデータマンといい、リライトはそのメモをもとに机上で編集意図と指定の文字数に合わせ、人を惹きつける原稿、いわば“商品”に仕上げる。
媒体によっては、リライターは最後の仕上げなのでアンカーマンとも言われる。アンカーは、手練れのベテランフリーライターで、後に著名な作家になる人も多い。
名手は限られているので、編集者はいつもとりあいだった。その編プロで信頼が高いリライターは、父のような年齢なのに少女向けの柔らかいものからシニア向けの医療記事やノンフィクションまでなんでも、魔法のように完璧な原稿に仕上げる。ボスは、今すぐその人に頼めというのだ。
「1週間前では受けていただけるかどうか……」ともごもごしていると、彼はいきなり電話をかけた。受話器の向こうの相手に何度も頭を下げている。申し訳無さと恥ずかしさと情けなさと悔しさが入り混じり、泣きたくなった。
あれが最善にして唯一の策だった。私は大事な媒体に穴を空けるところだったのだ。
そもそも、ここは学校ではない。
やる気だけを振りかざし、ゴールの高さも確認せず努力を怠ったぶざまな自分の胸に、ボスのシビアな指示は、ぐさりと刺さった。
はたらいてお金をもらうとはこういうことか。やる気だけでなしとげられるのは青春時代の文化祭までだ。
給料をもらってはたらくなら自分に厳しく。実力をわきまえて、足りないところを自力で一日でも早く補わなければ。同時に、緊急時に情に流されず的確に判断する能力も編集者の絶対条件だと学んだ。
・・・
失意の中、リライターの原稿をなんとか入稿して一息ついたとき、ボスに呼び出された。
「福祉のテーマや、ハンディを負いながら頑張っている人を描く原稿ほど難しい。泣かせようと思ったら読者はすぐ“臭さ”を感じ取って離れる。がんばる、努力、感動、ひたむき、精一杯、愛、涙。そういう言葉を一切使わずに人の心を動かす原稿を書いて初めて、お金をいただいて読んでもらえる商品になる。大平さんの原稿には全部入っていた」
おいしいと書かずに旨さを伝える。悲しい、さよならを使わずに別れを描く。愛と言わずに恋愛を書く。これはこの仕事に必要最低限、なくてはならない技術。それがなければ子どもの作文だと彼はつねづね説いていた。
あの5年で学んだことが私のすべての礎になっていて、忘れそうになると今もボスのいろんな言葉が降りてくる。自分が心地いいだけの安易な言葉に逃げていないか。一つ一つの原稿に高みを目指しているか……。
慣れによる奢りや失敗を忘れないために、私は恥を忍んでいつも冒頭の質問に隠さず答える。
「初めて書いた原稿は、ボツになりました」。
(写真/筆者提供)
| 大平 一枝さん SNSアカウント・ホームページ Twitter @kazueoodaira Instagram @oodaira1027 HP 『暮らしの柄』https://kurashi-no-gara.com/ |
本連載は、さまざまな筆者の「うまくいかなかった日」に関するエッセイを交代でお届けします。
スタジオパーソル公式Twitter(@hatawarawide) にて、最新の更新情報をご確認ください。

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。