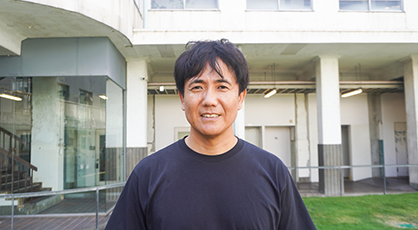両親にドラマの面白さを伝えたい。日本では数少ない「舞台手話通訳者」になった理由

第94回アカデミー賞の作品賞にも輝いた、映画『Coda コーダ あいのうた』を皮切りに、近年国内外で「手話」が登場する映像作品が次々と生まれています。映画『ケイコ 目を澄ませて』、ドラマ『silent』『星降る夜に』など、いずれも話題を集めた作品ばかり。そして、作品をきっかけに手話に興味を持ったという人も少なくないでしょう。
手話を使い、聴者とろう者をつなぐのが「手話通訳者」。音声でのスピーチを即座に通訳し、ろう者に伝える。情報保障の観点から非常に重要な存在であると同時に、手話を知らない聴者にとっても「ろう者とのコミュニケーションを助けてくれる」欠かせない存在です。
そんな手話通訳者の中でも、舞台での通訳を専門としているのが「舞台手話通訳者」という仕事です。脚本家である米内山陽子さんも、その一人。日本ではまだまだ数少ない舞台手話通訳とはどんな仕事なのか。手話通訳との違いは? 米内山さんのお話から伝わってくる仕事への姿勢は、私たちの仕事との向き合い方を考え直すきっかけをくれるかもしれません。
役者の「表現」を翻訳する舞台手話通訳者の仕事
アメリカやイギリスでは観劇サポートとして普及している舞台手話通訳。それが日本で初めてつけられたのは、1996年に上演されたウイリアム・シェイクスピア原作の『夏の夜の夢』でした。
以降、舞台手話通訳が定着していったかというと決してそうではありません。大規模な作品であっても、舞台手話通訳がつけられることは稀で、現在でも「年に数本というレベル」なのだそうです。
あまり目にする機会のない舞台手話通訳ですが、どのような仕事なのでしょうか?
「手話通訳は、聴者とろう者、双方の話していることを同時通訳するような仕事。一方、舞台手話通訳は『作品を翻訳して、ろう者のお客さまに見せる』というイメージが近いかもしれません。私は日本手話を使っているのですが、音声日本語とは文法がまったく違います。これらの異なる言語のセリフを翻訳しながら、お芝居の質を損ねないように気をつけなければいけない。そこが難しいポイントですね」

芝居の質を損ねない。それはつまり、作品世界の邪魔をせず、溶け込む必要があるということ。
「音声で喋る役者と、手話で翻訳する私。二人で1つの役を演じているんだ、という意識で挑んでいます。舞台手話通訳者はろう者のお客さまの目線を奪うことになるんです。それによって、役者が芝居に込めた感情が伝わらなかったら元も子もありません。なので、お客さまが私を観ていても面白く感じられるよう、役者と同様に感情表現をします」
米内山さんいわく、「舞台手話通訳は日本語吹き替えのようなもの」だそう。海外の映像作品を日本語に吹き替える声優は声の芝居をしますが、舞台手話通訳者は手話で芝居をする。ゆえに、役者同様、演出家からの指摘やリクエストを受けることもあります。
「パフォーマーとも言えるでしょうね。『ステージの端っこに立っていないで中に入っちゃって』なんて言われたり、役者と同じ表情を求められたり。役柄の裏の感情を出してほしいと注文されることもあります。だから、作品を通訳するためにはたくさん稽古を重ねなければならないんです。日常生活における手話通訳は語彙力が求められますし、一回限りの現場なので基本的に練習ができません。その点は大きな違いですね」
役者と一緒に感情表現をするだけではありません。舞台手話通訳者は、舞台上での音楽や効果音などを知らせる役割も担うのです。
「舞台上では、BGMや雨、風、雷といった効果音、電話の音などを表現することもあります。しかし、役者のセリフを翻訳しながら舞台上の音をすべて表現することはできません。なので、舞台手話通訳者には『なにを一番に伝えるべきか』という判断が求められます。演出家と相談しながら正解を見つけていくこともありますが、最終的には舞台手話通訳者のセンスに任される部分ですね」





ドラマの面白さが、はじめて両親に伝わったとき
米内山さんが舞台手話通訳者の道を歩み始めたことには、家族の存在が影響しています。米内山さんの両親は手話を母語とするろう者であり、彼女は「コーダ」として育ちました。コーダとは「聞こえない親に育てられた、聞こえる子ども」を表す言葉。日本には現在2万人以上のコーダが存在すると推測されています。米内山さんは幼いころから手話が飛び交う環境に身を置き、音声日本語と手話を身につけていきました。
「中学生の頃、三谷幸喜さんが脚本を手掛ける『王様のレストラン』というドラマが放送されていたんです。それが大好きで、毎週欠かさず観ていました。でも当時、テレビにはほとんど字幕がついていなかったため、耳の聞こえない両親には、このドラマの面白さが伝わらなかったんです。
そこで私は、録画したドラマを流しながら、その横で通訳してみせました。面白いと感じたセリフやシーンを分かってほしくて、一生懸命だったと思います。すると両親が笑ってくれて。『あなたの手話が良かった』ではなくて、『このドラマ、面白いね』と言ってくれました。それが本当にうれしかった」
同じ頃、ニュースの通訳をしてみたものの、ドラマや映画のようには喜びを感じられなかったそうです。当時からエンターテインメント作品への愛が深かった米内山さんが後年舞台手話通訳者になったのは必然だったのかもしれません。

自身の舞台から切り拓いた舞台手話通訳者としてのキャリア
日本では1996年の『夏の夜の夢』以降もなかなか定着しなかった舞台手話通訳ですが、2007年、米内山さんはふとしたきっかけである舞台の手話通訳を務めることになります。
「ある時、障害のあるアーティストが集まるイギリスの劇団、グレイアイ・シアター・カンパニーの演出家を招いて行う公演の稽古場に手話通訳者として呼ばれる機会があったんです。日本にはまだまだ舞台手話通訳が一般的じゃないんですと伝えたら、芸術監督から『あなたがやればいいじゃない』と言われたんです」
「私もやってみます」。反射的にそう答えた米内山さんがその言葉を実現させたのは、2011年のこと。劇作家として活動していた彼女は、プロデューサーに頼み込み、脚本を手がけた舞台作品で、自ら手話通訳を行いました。その結果、客席には想像を超える数のろう者の姿が。プロデューサーは「耳の聞こえない人がこんなに舞台を見に来てくれるなんて、今までなかったことだよ」と喜んでくれたそう。
「当時、ろう者が触れられる聴者の舞台というのは、多くはありませんでした。あったとしても、ろう学校時代に観た『お説教じみた作品』なんかが多かったみたいで。でも、私がやったのはライトコメディの作品だったんです。観に来てくれたろう者から『こんなコメディを手話付きで観たことなかった!』と言ってもらえたのがうれしくて、しばらくはコメディばかり作っていましたね。
その後もコツコツと舞台手話通訳を続けていったことで、大きなお芝居に呼んでもらえたり、取材してもらえたりするようになり、少しずつ認知が広がっていきました。最初の舞台から12年。ようやくここまで来れたかな、という思いです」
台本を翻訳し、稽古に参加し、演出家と意見交換をする。手話通訳者が舞台に立つとなれば、数ヵ月単位の拘束が求められる大仕事です。脚本家としても多忙を極める米内山さんが舞台手話通訳者を担えるのは、年に1~2作品ほど。それでも、足を運んでくれたろう者に心から楽しんでもらうためにと、米内山さんは全力を尽くしています。
また、自らが舞台に立つのと同時に、彼女は全国で開かれる舞台手話通訳養成講座での講師を務めるなど後進の育成にも力を注いできました。
「2年間で30名以上の舞台手話通訳者が生まれました。その後も全国各地で『私も舞台手話通訳をやっています』という声を聞くようになり、現在では50名ほどの舞台手話通訳者が活躍しているのではないかと思います」
「手話を消費しないで」。社会を前進させるために必要なのは、立ち止まること
手話通訳者の重要性が少しずつ社会に浸透し、聴者にとって手話は身近なものになってきていることは間違いありません。ただし、そこで絶対に忘れてはいけないことがあります。
手話を消費するのではなく、「ろう者の言語」として尊重することです。
「映画やドラマの影響により、現在は手話がブームになっているように感じます。実は手話ブームって、30年ほど前にも起きているんです。当時、ろうのキャラクターを主人公にした『星の金貨』『愛してると言ってくれ』といったドラマが放送されました。そして手話がブームになったわけです。でもそれっきり。一時的に流行るけれど、結局は忘れられてしまう。今はあの当時の熱狂を繰り返しているように見えます」
ろう者にとって手話がいかに大切なものなのか。それを理解しないまま「ブーム」となり、すぐさま飽きられてしまう。米内山さんはそんな現状を危惧しています。
「『手話ってすごい!』と盛り上がっては、忘れていく。そうやって手話という言語は消費されてきました。手話やろう者について知ってもらえて良かったね。ろう文化が広まってよかったね。なんて言われるのですが、知って終わりにするのではなく、もう一歩深めてもらいたいんです。ただ、こういった主張が手話へのハードルを上げることにつながるのではないか……と思うこともあります。難しいですよね」

手話を学ぶこと、ろう者と触れ合うことのハードルを上げたいわけではない。けれど、土足で踏みにじってもらいたいわけでもない。その複雑な思いを、米内山さんは吐露します。
「今、TikTokなどで手話歌が流行っているんですよ。ただし、その手話歌を披露しているアカウントは、歌詞に登場する単語を手話で並べるだけ。それでは、ろう者には通じません。音声日本語と日本手話の文法は異なるからです。
手を動かしながら歌って踊るのは楽しいし、やりたくなる気持ちもわかります。しかし、ろう者に伝わらない手話歌は誰のためのものなのか? それは善意による暴力ではないのか? 手話に関わるのであれば、一度立ち止まって考えていただきたいですね」
最近の手話ブームに対して、批判的な意見を持つろう者は少なくないのだそうです。彼らを前にして、「どうしてそんなに怒るんだ」と感じる聴者は少なくないかもしれない。そう前置きした上で、米内山さんは続けます。
「ろう者は手話がどんなに大切なものなのか、これまでに何度も何度も説明してきた。それなのにわかってもらえない。だから怒っているんです。社会はいつだって、マイノリティにばかり説明を求めます。それがいかに理不尽なことなのか、一度考えてもらえたらありがたいです。それが、社会を前進させるために必要なことなんですから」

耳の聞こえない両親の前でドラマの面白さを伝えようとしていた少女は今、舞台手話通訳者となり、日々奔走しています。彼女の活躍により、舞台手話通訳や手話の奥深さが広まる未来は、そう遠くないかもしれません。
(文:イガラシダイ 写真:鈴木渉)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。