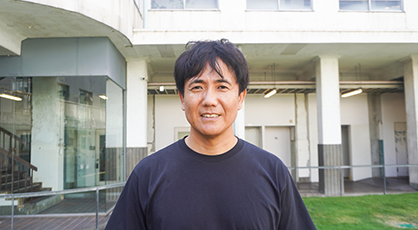日本でたった3人の「銭湯ペンキ絵師」。21歳で “覚悟”を決め、追い求めた夢

堂々とした富士山がトレードマークの銭湯のペンキ絵。それを手掛けるのは、全国でたった3人しかいない「銭湯ペンキ絵師」です。中でも、若き絵師として活躍する40歳の田中みずきさんは、全国各地の銭湯からオファーを受け、浴室の壁にペンキ絵を施しています。
それだけでなく、自動車メーカー「Audi Japan」やセレクトショップ「BEAMS JAPAN」など、PR関連のペンキ絵制作も担当。今年、2023年5月には朝日新聞で田中さんの特集記事が組まれるなど、数々のメディアでその活躍が取り上げられています。
今年、独立して10年が経ちました。今でこそ順風満帆に見える田中さんですが、大学生のころから修行を始め、試行錯誤をくり返しながら技術を磨いてきたと言います。
「(銭湯の)翌日の営業までに描き上げなければならないので、独立して間もないころは早朝から深夜までかかってしまったことがありました。今も師匠の制作時間よりかかっているとは思うんですが、夜になるぐらいには完成します。慣れてきたのは、本当にここ数年かもしれないですね。子どもが生まれて、『早く帰らないとまずいぞ!』という状況になってからが、1番変わったかもしれない(笑)」
はにかんだ笑顔でそう語る田中さん。いったい彼女はなぜ、銭湯ペンキ絵の虜になったのでしょうか――? 田中さんの道のりを聞きました。

絵を描くことが好きだった
1983年、大阪府で生まれた田中さんは、3歳のときに父と母、兄とともに東京都へ移り住みました。「子どものころは病気がちで、すぐ熱を出していましたね」と田中さんは振り返ります。
小学校1年生のある日、体調を崩した田中さんは、母親から少女漫画雑誌を買ってもらいます。読みながら、繊細な線で描かれた絵や物語の心理描写の巧みさに衝撃を受けました。
「そうだ、私も描いてみよう!」
その日から落書き帳を開き、漫画を真似て絵を描くように。気が付くと数時間が経っているほど集中していました。しだいに、美術作品にも興味を持つようになっていきます。それは、父の影響が大きかったそう。
「私の父は、新聞社で美術の記事を担当していたんです。休みの日にはよく美術館やアートギャラリーに連れて行ってくれました。父から『この作家はね……』って、子どもにも分かりやすいように説明してもらううちに、『この絵を書いた作家さん、こういう人だったんだな』とか、『実はいろいろ抱えている人だったんだな』とか、そこからアートの世界に興味が湧いてきました」

国立の小中高一貫校だったことから、そのまま中・高へ進学。高1の春、当時好きだったアート作品から影響を受けて「現代美術作家なりたい」と熱望し、美術系の大学に進学するための予備校に通い始めます。週3回ほど講習を受け、デッサンや課題の水彩画を描きながら黙々と腕を磨きました。好きなことに集中できる環境は青春そのものでしたが、少しずつ「自分の夢は狭き門である」と感じるように――。
「夏休みなどは、予備校には全国からたくさんの学生たちが集まりました。教室に行くとデッサンを描くスペースが埋まるほどで、『あぁ、これだけの人数の子たちが目指すとなると、美術館で作品を並べる作家になるのって、なかなかの競争率だな』って思って、気後れしてしまったんです」
田中さんは美大受験をあきらめ、明治学院大学文学部芸術学科に進学。「美術の歴史を知ることは、将来の強みになるのでは」と思ったことから、美術史を専攻します。この選択が、まさか「銭湯ペンキ絵師」につながることになろうとは、当時は思ってもいませんでした。
銭湯ペンキ絵との出会い
大学に入った田中さんは、美術史にドはまりしていきます。「授業で毎週1回質問する」というノルマを自ら課し、課題図書から講義内容に関する論文まで片っ端から読み漁るように。
卒業論文のテーマを考えていた大学1年の冬、たくさんの展示品や絵を見てきた田中さんは、ふと現代美術作家の福田美蘭さんの、ある作品を思い出しました。
それは、銭湯ペンキ絵をモチーフにしたもので、現代の企業ロゴマークが隠し文字として忍び込んでいるというユニークな作品。「思わずクスッと笑える感じでした」と田中さん。ほかにもさまざまなアーティストが銭湯の絵をモチーフにした作品を手掛けている背景があると気が付き、銭湯ペンキ絵に惹かれます。
それまで、銭湯に行ったことがなかった田中さん。好奇心から近所の銭湯に行ってみることに――。
暖簾をくぐって扉を開けると、目の前に番台があり、年配の女性が座っていました。入場料を払い、脱衣所へ。浴室に入ると、女湯の方に青い海が描かれ、男湯の富士山も、壁ごしに上部が見えました。身体を洗って浴槽に入ると、不思議な感覚に包まれます。
「湯気がもやもやっと上がって、ちょうど富士山の雲に重なったんです。正面で湯船に浸かっていたおばあちゃんが出ようとすると、お湯がゆらゆらと動いて、描かれた海の波と繋がっているような気がしました。『1枚の絵を空間で味わうことができるなんて、ものすごくおもしろいインスタレーション(展示空間を含めて作品とみなす手法)だな』ってびっくりしたことを覚えています」
その後、田中さんは大学の講義が終わると、都内のさまざまな銭湯をハシゴしては、ペンキ絵を眺めるようになりました。

100年先も残したい……銭湯ペンキ絵師の技術
銭湯の壁にペンキ絵が描かれるようになったのは、近代の明治時代ごろ。東京を中心とした関東近辺に広がり、「銭湯=富士山」というイメージが定着したと言われています。
昭和40年代のピーク時には、東京だけで2,800軒ほどあったと言われる銭湯ペンキ絵ですが、家にお風呂があることが当たり前になったことから、その数は激減。今では700軒を切るほどになってしまいました。この状況下で、銭湯ペンキ絵師は日本で2名だけになったのです。
大学3年の田中さんは、「卒業論文は銭湯ペンキ絵の歴史について取り上げよう!」と決め、情報を集め始めます。ある日、都内の商業スペースで、当時59歳の銭湯ペンキ絵師・中島盛夫さんのライブペイントが開催されることを知ります。
「えっ、本物に会えるなんて!」
そう思った田中さんは、ワクワクしながら見に行きました。実際に中島さんがペンキ絵を描くところを見て、感銘を受けます。イベント終了後、勢いで「今度、制作現場へ観に行かせてください!」と頼み込み、中島さんに連絡先を渡しました。
数日後、さっそく中島さんから連絡があり、都内の銭湯で行われる制作現場を見学。その後もたびたび中島さんの仕事場に顔を出すようになります。大学の授業で最後まで見ることができない時は、後日その銭湯に入りに行き、完成した絵をじっくり眺めました。
中島さんの仕事ぶりやペンキ絵を見続けて、田中さんはこう思いました。
「この技術が100年先に残らないなんて、惜し過ぎる……」
日本に数えるほどしかいない銭湯ペンキ絵師――。このまま誰も担い手がいなければ、消えてしまう職業だということは容易に想像できました。
論文制作が進み始めた大学3年、21歳の冬、田中さんは決断します。「弟子にしてください!」と、中島さんに申し込んだのです。けれど、中島さんからの反応は芳しくありません。「銭湯も減ってきていて、この仕事が何十年先まで続くのか予想できない。だから弟子は取っていないんだ」と断られてしまいます。
それでも納得できず、田中さんは再度食い下がります。
「仕事は……、ほかに何か食べていく方法を見つけます。技術だけでも、どうか教えていただけませんか?」
それを聞いて、渋っていた中島さんも「見習いという形でなら」と承諾。大学を卒業した田中さんはいったん大学院に入り、並行してペンキ絵の修業をスタート。2008年、大学院卒業後、美術系の出版社で編集業に携わりながら制作現場に向かいました。

「空」を塗ることの責任
銭湯ペンキ絵を描く現場では、いったいどんなことをしていたのでしょう?
制作の日は朝5時に支度をし、田中さんは師匠の車に乗せてもらって現場へ。荷物を運び、浴槽周りが汚れないようにビニールシートなどでカバーし、壁の前に足場を組み立てます。
銭湯の定休日は基本的に週1回のため、丸1日でペンキ絵を仕上げなくてはなりません。男湯と女湯の絵を併せて、ほとんどが10メートル×5メートルほどの壁。以前の絵を塗りつぶし、新しい絵を施します。
作業の合間に休憩時間を取るものの、猛スピードで仕上げていく師匠の姿を見て、田中さんは「す、すごい」と驚きを隠せませんでした。
浴室にエアコンはありません。夏は暑く、冬は寒さの中で作業します。自分の背丈より高い足場を行き来しながら作業するため、田中さんは「帰宅するころにはヘトヘトになっていましたね(笑)」と振り返ります。

それでもへこたれずに続けていたある日、中島さんから空を塗ることを任されるように。一瞬は喜びを感じたものの、ずーんとした緊張感がのしかかりました。一色のペンキで色を塗ることは一見簡単そうですが、実はとても難しい作業だったのです。
「ペンキ絵って、描かれた壁は何度も塗り重ねているので、ささくれのように捲れた部分を剥がすところから始めます。場所によっては何度も塗り重ねているので、新しいペンキがはがれやすかったり、凸凹としていたりするので、真っ平にムラなく塗るということ自体が難しいんです。当時は楽しさより、『師匠に言われた課題をこなせるだろうか?』という怖さの方が強かったです」
格闘していく中で、師匠から「今度は松、描いてみる?」と聞かれます。少しずつ絵の一部を任されるようになりました。「結局うまく書けなくて、その場で直していただいて(笑)。そこで『あ、こうすればよかったのか』って、だんだん分かるようになった感じでしたね」と田中さん。

修業に集中するために、田中さんのはたらき方は少しずつ変化していきました。ペンキ絵の制作は、たいてい銭湯が定休日の平日に行われます。出版社の仕事が土日休みだったことから、制作現場に通い続けるのは限界があったそう。1年半ほど勤めますが、体調を崩したことも重なって出版社を退職。
その後、実家で暮らしながら平日にビジネスホテルのフロントでアルバイトをし、空いた時間に大学時代の友人に誘われたアート系のウェブメディアのライティングや編集の仕事を始めました。「生計は別で立てる」と師匠に約束をしたからこそ懸命にはたらき、修業に集中する環境を整えました。

独立し、夫婦二人三脚で歩む
修業を始めて9年後の2013年の春、師匠から独立。田中さんの新たな挑戦には、帯同してくれる頼もしい存在がいました。公私ともに信頼を寄せるパートナー、便利屋を営む駒村佳和さんです。
駒村さんとの出会いは、2005年の秋。吉祥寺の銭湯で開かれた音楽イベント「風呂ロック」でした。当時、大学院生の田中さんはそこで手伝いをしていました。6歳年上の駒村さんは、同イベントでステージの機材の運搬などを担当。以前まで工事現場などで金属の足場を組み立てるとび職をしており、独立資金を貯めるべくさまざまな仕事を引き受けていました。
ただ、2人は数カ月間、知り合い程度の関係でした。ある日、田中さんの知人の木工職人が家を手作りすることになり、壁を塗る手伝いに行くことに。
「人様の家の壁を素人が塗っていいのかな……。足場を組む仕事をしていた駒村さんなら、いろいろ相談できるかもしれない」
そう思ったことから声をかけてみると、駒村さんは快く引き受けてくれ、現場に同行してくれたそう。その後、親睦が深まり、お付き合いが始まりました。

独立して間もない2013年に結婚。そのころ、田中さんは銭湯ペンキ絵師として仕事が次々と舞い込むようになっていました。修業時代から書いていたブログを読んだ銭湯の店主から、問い合わせがくるようになったのです。
アルバイトをする暇がなくなり、数カ月後には銭湯ペンキ絵師1本でやっていけるほどに。制作現場での足場作りを駒村さんに仕事として依頼し、浴槽の上で作業をする安全性も保てるようになりました。「彼がいなければ、私の仕事は成り立ちません」と言うほど、今も二人三脚で歩んでいます。

腐らずやっていると、意外に見てもらえている――
独立から10年が経過した今、ペンキ絵の依頼が増えた理由を田中さんは次のように語ります。
「今まで銭湯のペンキ絵って古いイメージがあったけど、一周回って『ペンキ絵って味があっていいよね』と、若い世代の店主の方々が依頼してくださることが多いんです。スーパー銭湯や温泉旅館からも、『湯処のイメージにいい』と新鮮に感じていただけるようになりました」
若き銭湯ペンキ絵師として、期待を寄せられていることも大きな理由でした。
「独立当初、銭湯店主さんから『若者が出てきたから、ちょっと応援してあげよう』という気持ちで、お話をいただけるのがありがたかったですね。『もっといい絵が描けるように』とがんばり続けていたら、翌年も依頼をいただけて、別の銭湯も紹介してもらえるようになりました。『自分の仕事なんて誰も見てないよな』と思っていたんですけど、腐らずやっていると、意外に見てくださっているんだなって」
取材当日、銭湯ペンキ絵の修行をしている山本奈々子さんが現場でサポートに入っていました。「以前、直接連絡をもらってアドバイスさせてもらったころからの縁です」と田中さん。彼女は田中さんの一挙一動を食い入るように見つめ、何度もメモを取っていました。修業時代の田中さんも、きっとそうしてきたのでしょう。

「まだまだ経験が足りないので、田中さんの仕事を近くで見られるのはありがたいです」と山本さん
この仕事で大切にしていることは、打ち合わせと下準備だといいます。銭湯ペンキ絵の依頼を受け、制作日の約1カ月前には店主と相談。今回制作した銭湯では、1年かけて準備を進めたと言います。悩んでいたり、多くの要望があったりする場合は、手書きで描いた3案のイメージ図を事前に用意するそう。
「ご要望のまま描いたもの。あえてスタンダードなもの、そして、こちらから提案したいもの。この3案を出すと、『この絵のこの辺りを変えたい』と店主の方から言葉が明確になって、その銭湯だからこそのブランディングが見えてくるんです」
とことん時間をかけて準備する彼女だからこそ、多くの人に信頼され、リピーターが増えているのかもしれません。「一件ずつ、お付き合いが深まっているのを感じます!」と田中さんは言います。

私生活では、2021年4月に長男を出産。現在3歳になる子の育児の真っ最中です。仕事と妊娠、出産の両立は大変なものでした。
「銭湯のペンキ絵は塗料を溶かすための薬剤を使います。胎教に差しさわりがあるかもしれないので、妊娠中の丸々1年くらいは制作することができなかったんです。そういうこともあって、『(金銭的な部分で)どうやって生活していこう?』というのが大きな問題でした。せっかくお話をいただくのにお断りすることが重なって、『今までやってきていたことができなくなるのでは』と焦りを感じましたね」
この期間は、薬剤を使わない水性ペンキで対応できる地域でのライブペイントを引き受けたり、出版社からオファーがあった自伝本に取り組んだりなど、できることに挑戦しました。2021年の5月には、『わたしは銭湯ペンキ絵師』を出版。等身大の田中さんの思いが綴られています。
アートの魅力を教えてくれた父、銭湯ペンキ絵を背中で見せながら学ばせてくれた師匠、心強いパートナーである夫、そして、いつも応援してくれる人たちの存在――。出会った人たちに感謝しながら、田中さんは今日も銭湯の壁に向き合っています。
(文・写真:池田アユリ 画像提供:田中みずきさん)

※ この記事は「グッ!」済みです。もう一度押すと解除されます。